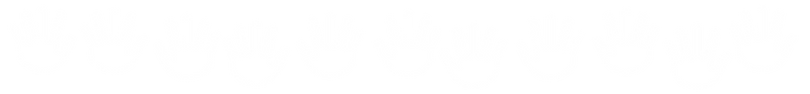
「は…!!っ、ぁ…!はあ…!!」
道などもうとっくに見失ってしまった。
背後へ流れていく木々は夜に暗く沈み不気味にザワザワと蠢き揺れる。
足首に纏わりつく雑草を蹴散らし、砂利道を無視して真横に突っ切ってそのまままた草木の中へと飛び込む。
耳を掠めた枝がヒョウと啼いた。
夜を彩る虫たちが涼やかな求愛の音色を奏でる中、爛と光る瞳が闇に沈みきれず歯ぎしりと共にチカチカと揺れた。
息を殺して身を縮める。
合宿用の手に馴染んだ鞄。
それと、つい先ほど支給されたばかりのデイバックの固い感触を抱きしめて荒い息を整えようと苦労した。
空からは赤い三日月がジッと頭頂辺りを見下し見つめてくる。
その光からすら隠れるようにそろそろと大きな木の幹の後ろへ地面へ這いつくばったまま移動した。
人の気配は、無い。
カサカサと手元をなにか昆虫のようなものが横ぎったのは感じたがいちいちそんなものに意識を向けている余裕があるわけもない。
首に巻き付いた、銀色の首輪が木漏れ日のように差し込む月光に反射し、日向は、その光を嫌って更に闇へと沈む。
そいつのせいなのか、なんだかやたらと息苦しい気がした。
「はぁ…、ひゅ…、は…、」
食いしばった歯の間からヒュウヒュウと風切音のような呼吸を繰り返し、項垂れ、
「ぐ…、」
込み上げてくる吐き気に口を覆えばべったりと手にこびりついた粘つく液体がツンと鉄臭い生臭さで鼻をついた。
夜気に冷えて渇き始めるソレは、まぎれも無い人の、血液だった。
「…ぁ、…あ、ひ、」
込み上げてきた悲鳴を飲み込む為にデイバックのストラップへ白い歯をぎちぎちと突き立てる。
そうしていないと今にもガチガチと激しい震えで鳴りだしそうだった。
どうしてこうなったのか。
わからないのは日向ばかりではなかっただろう。
どこかから人の足音がして。
ギクリと見開いた目は宙を凝視して小さな身体はギュッと固くなる。
荒い息遣いと、まろぶ足音は一度派手に転倒してすぐ立ち上がり、木の根元に縮こまる日向には気が付くこともなく目の前をかなりのペースで駆け抜ける。
学校鞄を背中に背負い、日向の抱くのと揃いのデイバックを掴んだその人は伊達工業のユニフォームを着ていた。
見覚えの無い選手だった。
可能な限りの速さで闇を突っ切っていくその姿が今は、日向にはどうしようもなく恐ろしい。
ふっ、ふっ、
うるさい呼気は己のものだ。
伊達工のあの人はどこへ行くのだろうと耳だけで音を追い、首を振ってその先を考えるのを辞めた。
声をかけるべきではないと判断したのは、もしかしたら彼に“殺されるかもしれない”と思ったからだ。
どうしてこうなったのだろう。
二度目の思考とじわりと滲む視界の中で、赤く染まった両手を見つめおろす。
闇の中でもその赤さは見間違えようがなく、大切な友人をひとり、己は失ってしまったのだという痛感に日向は声を殺してひたすらにむせび泣いた。
地へ伏せて、鞄に顔を押し付けて静かに。
「研、磨…!!」
囁きにも似た呻き声は誰にも聞きとがめられることなく木立の中へと紛れて消えた。
~・~
とても楽しみにしていた遠征合宿。
夜に出発するという非日常の行為に、日向は紅潮する頬を冷やす事も出来ずにバスに足早に乗り込んだ。
運転手はバレー部OBの滝ノ上。
銘々がそれぞれ好き勝手な席へつく。
一瞬、迷った日向がなんとなく、空いていた縁下の隣りへ「失礼します」と言って座ったのは前回の遠征以来、影山と少し気まずい事になっているからだった。
ここ数日、ふたりの様子が少しおかしい事に気が付いていたのだろうか。
縁下はなにも聞かずに日向を隣に座らせてくれた。
しかしチョコンと、席へ座るなり。
落ち着きなくきょろきょろと頭を動かす日向が、なんとなく目線を飛ばすのはやはり、影山の方だったりしたのだけど。
影山は、日向より少し後方の席で窓枠に肘を突き、いつもの不愛想な顔で夜の景色をただボヤッと見つめているようだった。
空っぽの隣の座席には、影山の合宿鞄がぞんざいに放り出され空虚な隙間を埋めている。
いつもなら、日向が座るべき場所だからか、誰もそこには座っていない。
なんだかその光景に、わけもなく悪い事をしたような気持ちになる。
影山を一人ぼっちにしてしまったような罪悪感。
ふと、影山がなんの気まぐれか姿勢を変えようとついていた肘をおろした。
その黒い瞳が不意に日向の方へ向けられるのを瞬間的に感じて、日向が慌てて目をそらす。
後頭部へビシバシ視線が刺さっているような気がしたが必死になって気付かないふりをした。
ただの旅行やなんかとはコレが、違うものだとは部員たちは全員よくわかっていたがやはりまだ遊びたい盛りの少年たち。
日常と違う状態に置かれれば否が応でも子供心がソワソワと疼きだしジッとなんてしていられない。
バスが走り出ししばらくすれば、車内はすぐ元気な少年たちの賑やかな歓声と笑い声、楽し気な騒音に包まれ活気があまりあるほどに溢れかえった。
どこかでペプシの蓋がプシュッと音を立てればまたどこかでポテチの袋がパンッと弾け、夕飯は家でしっかり食べてきたはずの生徒たちの胃袋がまた一回り内圧で膨らむ。
冗談を言い合い、互いをくすぐりあい、あちらこちらで時折ドッと一斉に笑う声が響く。
きっと前回もこんな感じだったのだろうなと調子に乗った田中に揉みくちゃにされた日向はウキウキと弾む気持ちで思い、その隣の縁下がそろそろまずいなと苦虫を噛み潰した顔をしかけた辺りで澤村の、それでも怒号ではない叱責がいつもの通りに飛ばされた。
固い座席はとても上等なベッドとは言いがたい。
それでも育ちざかりの少年たちへ睡魔は優しく訪れて眠りの底へゆるゆると彼らを順序良くいざなう。
騒音が満ちに満ちていたバスの車内にもやがて穏やかな静寂が訪れて、ソッと照明が落とされた。
灯りを落としたのは武田だった。
同じようにぐーすか腕組みをして寝息を立てているのはコーチである烏飼だ。
きっと朝早くの畑の手伝いで疲れていたのだろう。
寝冷えしないようにと、ブランケットをかけてやり武田も自身の席へ戻る。
斜め前、運転席から「先生、」と声をかけてくる滝ノ上は運転手なので勿論の事眠れるわけがない。
「先生は寝ててもいいっすよ。明日は、俺は寝てられますけど先生はずっとアイツらのお守りでしょ?」
「うーん…いえ、しかしお気持ちだけいただいておきます。お願いした手前、寝ようと思ってもどうにも…心苦しくって眠れそうにもありませんから。せっかくですから、眠気覚ましに話し相手でも務めますよ?」
「ははっ、真面目ですねぇ。んじゃま、万が一眠くなるようなら寝ちゃってくださいよ」
居眠りしたらゴメンネ。なんて滝ノ上は言っていたけれど、生徒たちを起こさないよう小声で交わす会話のおかげもあってか目は冴えているようだ。
ボソボソと囁き合う会話は話した先から忘れていくような日常のもの。
一昨日は天気が良かったおかげで洗濯物がよく乾いただとか、どこかのお店で特売の卵が安くてだとか。
他愛もない言葉をつらつらと口にする。
ふと、会話が途切れる僅かな瞬間。
鼓膜に届く生徒たちの穏やかな寝息に、武田が慈父のような横顔を覗かせた。
体格はもう、すっかり大人と並ぶほどの身長であったとしても彼らの寝顔はまだ幼さを色濃く残し、思春期特有の成長意欲から自らの意思で強固に形成されていた個性という名の表層を、すっかり脱ぎ落した隙だらけの表情はどれも素直で優しい色に満ちていて、まさしく平和そのものだった。
「目を覚ます頃には、到着してそうですね」
高速道路。
等間隔に並んだ水銀灯が眼鏡に反射してチラチラと光る。
そのオレンジ色の暖かな光で、腕時計をチラリと確認してから武田はポツリと無意識にそう呟いていた。
~・~
「は…ッ!は…」
校舎の外へ出て、まず最初に国見がしたのは自らのデイバックの中身の確認だ。
最後の独りになるまで殺し合え。
これは生死をかけた椅子取りゲームだ。と。
ある日唐突にそんなゲームを強要されて、あっさりそれを納得し受け入れられる人間なんてものはまずいない。
最初はそれこそ、これは自分の見ている性質の悪い夢だと思った。
間違いなく全て現実なのだと思い知らされて尚、どうあってもこんなゲームには参加してやるものかとも考えた。
しかしそんな思考は全て虚勢だったのだと、容赦なく目の前で虫けらみたいに人が殺された瞬間にハッキリとわかった。
飛び散った色は鮮やかな赤だった。
怒号と悲鳴、泣き叫ぶ声。
駆け寄る足音と逃げ回る足音、机の倒れる派手な騒音。
ケンマと呼ばれた少年の真っ白な、唇から赤い筋がトロリと落ちた。
強烈な色のコントラスト。
破裂した首からはドクドクと脈拍と同じリズムで鮮血が溢れ続けていた。
胃が急降下していくような錯覚と、心臓が凍り付く幻聴に指先が痺れてフルフルと震えた。
彼は、音駒、という東京の高校の2年生だったらしい。
そうとわかったのは彼が公式試合の際着用するユニフォーム姿だったからだ。
国見自身、今はどうしてか青葉西城のユニフォーム姿である。
自分で着替えたような覚えは無かった。
きっと眠っている間に着替えさせられたのだろう。
そして首にはその際、一緒に装着されたのだろう銀色の首輪がある。
音駒の彼は、その、首輪が爆発した事で十字にかけられた聖人のように、仰向けに倒れる羽目になったのだ。
あの、プリン頭の赤ジャージ。
猫のような瞳を開いたままで、ポカンと天井を見上げたままで、トサカ頭の赤ジャージに必死に名を呼ばれ続けていた。
その元凶を作ったのと同じものが己の首にかかっているその事実を思い出し、吐き気で奥歯をぎちぎちと軋ませる。
泣いても騒いでも叫んでも暴れても、助けなど来やしないという認識は既に国見の中に芽生えつつあった。
一体、何人が同じような思いで今、〝この島”にいるのだろう。
やらなければ、やられる。
「クソ…なんで、こんな事に!!」
焦る手が震え、デイバックの中をうまく探る事が出来ずに苛立ちからデイバックを天地さかさに返す。
中身が重い音、軽い音をたてながら地面の上へとブチ撒けられた。
その物音に高ぶった神経がキリキリと削られていくのがわかる。
無言のままで、周囲の様子を伺った。
学校を飛び出してどれほど走ったか、距離は長くも感じたが短くも感じた。
たまたま目についた倉庫の裏に駆け込んだだけの今の状況はとても安全とは言いがたい。
もう少し、遠くまで走って安全を確保してからの方が良かっただろうか?
それとも、鍵のかかった倉庫の窓を、叩き割って侵入した方が良かったか?
気持ちばかりが急いていく。
月明りすら届かない影に潜み、ジッと闇に眼を光らせた。
シンと誰の気配も無い夜の空はザワザワと木々が風に騒ぐ音と虫たちのさえずりだけを抱いていた。
人の、気配はどうやら無い。
ふー…っ、と長く、息を吐く。
気を取り直し、手を地面へ蠢かせてたった今引っくり返したばかりの中身をひとつひとつ手に取り確かめていく。
荷物は、1リットルの水のペットボトルが2本。
実に不味そうな粗末なパン。
おそらくは今自分たちがいるこの島のソレと思われる新品の地図。
方位磁石、時計。
実用性だけで飾り気のない懐中電灯。
それに、
「コレか…?」
日常の中にいてもよく見かける物たちの間に、映画の中でしか見たことのないような物体がゴロリと無造作に転がっていた。
ソロリと手を伸ばし、一度ためらってから、試しに持ってみるとズシリと手に重い。
イサカM37のソードオフ。
ショットガンだった。
それは“学校”であの“教師”からデイバックにランダムに入れてあると言われた、人を殺す為の道具に違いなく、そしておそらくは“アタリ”という奴だ。
武器にはアタリとハズレがあるらしい。
ヒヤリと冷たい鉄の感触に口内にジワリとツバが湧きだしてそれをゴクリと無理矢理に嚥下する。
我知らず瞳孔がキュウッと開いた。
緊張に、ジワジワと手の平が汗ばんでくるのが分かった。
左手でイサカM37を抱えなおし、右手を乱暴にユニフォームの腹で拭う。
懇切丁寧に取扱い説明書が入っていたのがまた悪い冗談のようだ。
いくつか一緒に転がり出てきた細長い筒を拾いあげる。
コレが弾丸というやつなのかと、しげしげと眼を細め闇の中で見つめてみる。
映画で知っている、ロケット型のものではなく、本当にただのプラスチックの筒に見えた。
金属の部分は一部だけだ。
しかし見た目よりもずっと重い。
国見が知るはずも無かったが、ショットガンは元は狩猟目的の銃である。
プラスチック製の筒の中には多数の小さな弾丸が詰まっており、それが火薬に押され銃口から飛び出し散開発射する仕組みになっている。
カラカラとソレらを掌中で弄ぶ。
銃の中にもどうやらあらかじめ弾丸が入れてあるらしい。
注意は完全に手の中の武器に注がれていた。
そのせいで、背後の気配に気が付くのが遅れた。
誰か、自分以外の息を飲む音を聞く。
ハッとして振り向いた先に赤い、あの“爆発した”音駒高校生と同じユニフォームの男子が独り、立っていた。
冷や汗にびっしょりと濡れた顔。
ぶるぶると震える身体の、その、右手の辺りの何かがキラキラと月の光を反射している。
何か持っている。
国見がその時考えられたのは、ただ、相手の持っている武器の事だけだった。
月光を反射出来るという事は、おそらくあれは鉄製の何かなのだろう。
もしかしたら、自分と似たような武器なのかもしれない。
銃か?
もしそうなら、もし相手が、もし今、もし、
此方に向けて発砲したとしたなら。
俺は?
小柄な彼はまだ1年なのだろうか?
自身も1年である国見から見てもとても小柄な相手に見えた。
黒い髪は脱色した形跡もなく、良い子の代名詞のような切り揃え方をしている。
「ぅ…!!」
どちらが先に動いたのだろう。
男子の腕が動くのを見た国見の腕もまた咄嗟に動いてしまっていた。
明確な意思など無いにも等しい。
双方、ただ怖かっただけだ。
風船が破裂したような音は1発だけで、反動でドンッと身体を突き飛ばしてきたイサカM37に驚いた国見が思わず大きくよろけ、尻もちをつく。
構造上、散弾銃というものは正確な射撃が出来ないものではあったがそもそも訓練を受けていない素人に正確な射撃なんて望めるはずもなく、むしろ、狙って撃たずとも放射状に発射される弾が面で標的を襲う散弾銃は素人の使用にこそ優しいものだ。
少々狙いが雑であっても標的に向けて引き金を引けば半径数メートル射程内をほぼカバーしてしまう。
ちょうど、棒をただ獲物に向かって向ける、というようなイメージで使うものであり、正しく使えば、あやまたず獲物を仕留める事が可能な物でもあった事はこの場合国見にとって良いことだったのか。
否か。
幼い頃、遊んだ花火の燃えた後のような匂いがツンと鼻の奥を突いた。
痛みより懐かしさが胸に去来する。
細い白煙を上げる銃を抱いた国見の、両膝がガクガクと力なく揺れた。
上手く立ち上がれず、痺れる手を叱咤するようにイサカM37を握り直す。
「…ね、ちょっと」
大丈夫?と、喉まで出かかってくる言葉を無理矢理飲み込む。
そんな言葉をかける場面じゃないとかろうじて気付く。
さっきまで。
目の前で震えていたはずの男子が地面に倒れているのが見えた。
嘘だろう?
嘘だろう?
頭の中では現実を否定する自分の声がわんわんと響く。
ふらつく足が、自重に耐えきれず何度も身体を地面へ凪ぎ倒した。
這いつくばったまま、ソロリソロリと近づく。
覗き込んだ、音駒高校のユニフォーム姿の彼の、顔は、
あの、素直そうで、恐怖に濡れていた顔は、
白と赤の肉の塊に変わっていた。
「ぅ…!おげ…!!」
イサカM37を抱えたまま、眼をそらしたその先で胃の中身を全てブチ撒ける。
鼻の奥がツンと突き刺すように痛んだ。
苦味と酸味が舌の上で粘つき、それを手で押さえ込もうとしたせいで跳ねかえった物がドロドロと顔を汚す。
こんなつもりじゃなかった。
そう思うのに。
震える身体は止まらない。
見なければ良かった。
見るんじゃなかった。
やってしまった。
やってしまった!
真っ白に漂白されていく思考はそれでも懸命に生にしがみつく。
なるべく男子の方は見ないようにして、キッと前だけを睨みつけ地面へ広げたばかりの荷物へ駆け戻り、ふと気が付いて地べたで乱暴にゴシゴシ汚れた手を拭った。
自分でも、馬鹿な行動だとは思った。
手あたり次第に、ブチ撒けていたデイバックの中身を全て掻き集める。
痺れたようにうまく動かない手で無理矢理に所有物をぎゅうぎゅうと詰め込んだせいで水のペットボトルでパンがぺしゃんこに潰れたがそんな事どうでもよかった。
その場からとにかく逃げ去りたい一心で、鞄ふたつを肩でひとまとめに。
イサカM37を余った手に掴んだままでクラウチングスタート宜しく、駆けだした。
がむしゃらに懸命になって地を駆けながらもう1度、なんの気の迷いか肩越しに振り向いた。
ほんの一瞬だけ見えた背後の景色。
男子の手には、キラキラ光る銀色の、手錠が握られていた。
~・~
続
~・~